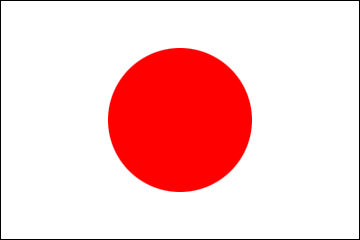レオン・デュリー(M. Léon DURY):幕末から明治維新期における日仏関係及び日本産業の近代化に貢献したフランス人
1 レオン・デュリー
 レオン・デュリー
レオン・デュリー
(1)1822年にプロバンス地方のランベスク(Lambesc:マルセイユの北方約40km)で生まれたデュリーは、マルセイユの大学で医学を学び、医師となる。クリミア戦争に軍医として従軍(1853-56年)した。幕末期に江戸幕府が函館での病院建設を計画したベルクール駐日フランス公使に病院長を務め得る医師の派遣を依頼、それを受けてデュリー医師が1862年に来日した。
(2)しかし、デュリーが来日した時点では既に病院建設計画は中止になっていたため、フランス政府は同人を在長崎のフランス領事に任命した。長崎では領事としての公務の傍ら日本人にフランス語を教える活動も行った。滞在中、大浦天主堂の建設にも関わった。また、1867年のパリ万博に派遣された徳川民部太夫一行の案内役を果たしている。その後、在長崎領事館の閉館に伴いマダガスカルへの転勤を命じられたが、デュリーはこれを拒否し、京都府が創設したフランス学校の校長兼教師になる。同校の閉鎖後は東京に移り、開成学校(後の東京大学を構成する前身機関の一つ)で教師を続ける。
(3)デュリーの京都勤務時代、府知事からの依頼で1872年に西陣織工の3名が絹織物産地のリヨンへ派遣される。うち1名は帰国のために乗船していた船が伊豆沖合で沈没し、死去したが、先に帰国していた残り2名が最新織機ジャガードをデュリーのはからいで持ち帰り、西陣織の近代化に貢献した。デュリーは1877年の帰国に先立ち京都府知事に対し、新しい日本を作る有為な人材を育成するためにはフランスで最新の知識と技術を学ぶ必要があると進言。府知事により選抜されたのが、染色、織物、製麻、製糸・撚糸、陶器、機械、鉱山、絵画・図案を学ぶべく選抜された8人の若者であった。京都府はデュリーの人格を絶対的に信用し、留学生の学科の選定から一身上のすべての事柄の保護監督、留学費用の管理をデュリーに委任した。デュリーは8人の若者を伴い帰国し、一行はマルセイユに到着。8人の京都の若者はまずマルセイユの学校でフランス語を学習した後、それぞれの専門分野の習得地に赴いた。留学期間は3年ないし4年であった。休暇の時期はデュリーの生家(ランベスク)で過ごすこともあった。うち、鉱山を学んでいた歌原重三郎は病を得て留学先の仏中部サンテティエンヌで逝去し、遺骸はデュリーの故郷に移されデュリー家の墓地に埋葬されている。
(4)こうした功績もあり、日本政府は1885年に勲四等旭日章を叙勲、1888年にはマルセイユの日本名誉領事に任命した。1891年に故郷のマルセイユで逝去(享年72歳)。デュリーの教え子たちは1899年にその師の功績をたたえるために「レオン・デュリーの碑」を京都南禅寺に建立し、現在は関西日仏学館内に移設されている。
【デュリーが監督した8人の日本人留学生の1人である稲畑勝太郎貴族院議員・大阪商工会議所会頭の喜寿記念伝記「稲畑勝太郎君傳」に基づく】
2 ランベスクに残る日本関係施設等
(1)デュリーの生家
デュリーが京都から引率した日本人留学生は、休暇の時期にはデュリーの生家で過ごした。デュリーに子はなく、彼の死後は妹が生家を引き続ぎ、日本人留学生の世話を続けてきたため、村では「ヴィラ・ジャポネーズ」(日本人の家)と呼ばれていた。この妹にも子がなく、生家は教会に寄贈され、現在は修道女の寮として使われている。
(2)博物館
ランベスクの町の歴史にまつわるものを展示する市営の博物館(Musée du Vieux Lambesc)では、同市出身の在日本フランス領事の遺品として、デュリーが日本から持ち帰った品々も展示されている。
(3)デュリー家の墓
デュリー家の墓は、上述のとおり妹の死後は親族が絶えたことから、現在は市が管理をしている。最近も外壁の修理を行っている。墓を囲う建物の正面には桐の紋と「LES JAPONAIS RECONNAISSANT A LA FAMILLE DURY(日本人はデュリー家に感謝します) 」と刻まれている。上述の歌原重三郎のハート形の墓碑も建物内部の壁に設置されている。
(4)地元の研究家
ランベスク出身の歴史家シャーブル氏(Mme. Sandrine CHABRE)がデュリー氏のことを研究しており、生誕200周年の2022年に研究成果をまとめて出版すべく準備中とのこと。